【音楽】30代になると、昔の歌はよく覚えているのに最近ヒットしている曲を覚えられなくなるのはなぜか
【音楽】30代になると、昔の歌はよく覚えているのに最近ヒットしている曲を覚えられなくなるのはなぜか
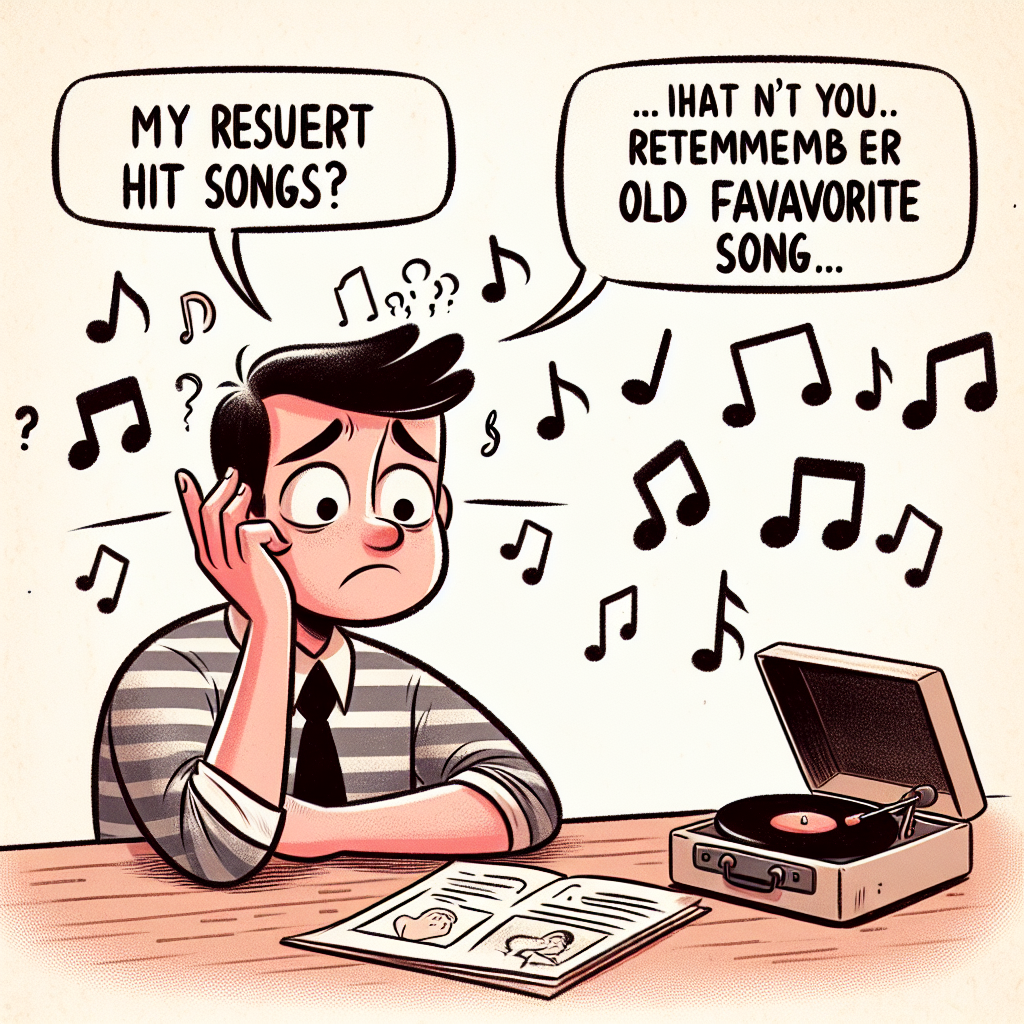
8/13(水) 12:00
「10代20代の頃流行していた歌はいくらでも覚えているのに、30代に入ったあたりからヒットしている曲を全然覚えられなくなった」という人は多いのではないでしょうか? この背景には記憶の心理メカニズムが働いているとか。心理学者・榎本博明氏による日経プレミアシリーズの新刊『なぜあの人は同じミスを何度もするのか』から抜粋します。
昔の歌はよく覚えているのに、最近の流行歌はいくら聴いてもなかなか頭に入らない。それは多くの人が感じていることなのではないだろうか。いろんな年代の人が一緒にカラオケをするような場面で、年配者が必ずと言っていいほど口にするのが、「最近の歌は全然頭に入らない。昔の歌しか歌えない」といったセリフである。
カラオケをする際、何十年も聴くことのなかった曲でも、その曲が流れ始めると、自然に記憶が蘇り、映し出される歌詞を見ながら何となく歌えることが多い。歌っているうちに、だんだんと記憶がよみがえってきて、歌詞を見なくても歌える曲もあったりする。ところが、最近の曲となると、毎週見ているはずのテレビドラマの主題歌であっても、なかなか歌えない。若い頃は、何回か聴けば歌えるようになったのに、どうにも頭に入っていかない。このような話をすると、まさに自分もそうだとだれもが言い出し、同じようなことを思っている人が非常に多いことがわかる。
(中略)
そこで、一応専門家として、記憶の心理メカニズムについて簡単に解説した。その概要は、以下の通りである。
まずはじめに浮かぶ疑問は、最近の歌を聴いてもすぐに忘れてしまうような人が、なぜ昔の歌をずっと覚えていられるのか、というものだ。記憶力が減退しているのなら、古い記憶も消えてしまってよさそうなものなのに、なぜ昔の歌は覚えているのか。この疑問は、記憶の基本的なプロセスに深くかかわるものと言える。記憶のプロセスは、記銘→保持→再生という流れでとらえられている。
記銘とは、何らかのことがらを心に刻む機能、つまり覚えることである。保持とは、記銘された内容を維持する機能、つまり忘れないようにすることである。再生とは、保持されている内容を引き出す機能、つまり思い出すことである。(中略)
冒頭のエピソードに戻ると、年をとるにつれて最近の歌が頭に入らなくなるというのは、「記銘力が弱くなる」ということを意味している。
若い頃の流行歌は聴けばすぐに覚えられたというのは、記銘力が存分に発揮されていたために、すぐに記憶に刻むことができたのだ。
全文はソースをご覧ください

